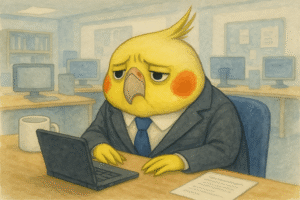新年度が始まって1か月──
「なんとなくやる気が出ない…」
「最近、社員が元気がない気がする…」
そんなふうに感じたことはありませんか?
それ、もしかすると“五月病”のサインかもしれません。
今回は、企業の経営者や人事担当者の方に向けて、
「五月病」とその背景にあるストレスの正体、職場でできる対策について、
社会保険労務士の視点からわかりやすくご紹介します。
💡五月病とは?
「五月病」とは正式な医学用語ではありませんが、
ゴールデンウィーク明けに見られる心身の不調を総称したものです。
- 朝起きるのがつらい
- 出社する気力がない
- 仕事のやる気が出ない
- 集中できない
- ミスが増える
こうした症状が、4月に張りつめていた緊張感の反動として現れることが多く、
新入社員や異動・昇進した社員に限らず、誰にでも起こり得ます。
🧠五月病の正体は「ストレス」
五月病」の裏側にあるのは、慢性的なストレスです。
🔎ストレスとは?
ストレスとは、心や体に負担がかかることで生じる反応のこと。
このストレスの原因を「ストレッサー」と呼びます。
たとえば
- 📋 業務量の増加
- ⏰ 長時間労働
- 🧑🤝🧑 新しい人間関係
- 📉 評価プレッシャー
こうしたストレッサーに気づかないまま無理を続けると、
社員のモチベーションや生産性が大きく低下し、離職やメンタル不調につながることも。
🛠️企業ができる五月病対策
✅ 変化に気づける「声かけ」を
社員のちょっとした変化に気づくには、
日頃の声かけや雑談の中での観察力が重要です。
- 「最近どう?」と一言添える
- 表情や返事の様子をチェック
- 新入社員には週1回の1on1を
✅ ストレスチェック制度の活用
年1回のストレスチェックを、ただの義務にせず、
職場環境改善のきっかけとして活用しましょう。
- 結果をフィードバックして終わりにしない
- 高ストレス者への産業医面談などを整備
- 部署ごとの傾向を分析し、業務改善に反映
✅ メンタル不調時の対応マニュアルを整備
「いざ」という時に備えた社内対応マニュアルの整備が重要です。
産業カウンセラー資格を持つ社労士なら、
メンタルヘルス体制の整備や社員研修にも対応できます👩⚖️
🌼身近にできるストレス解消法(コーピング)
社員自身ができるストレス対策(=コーピング)も伝えていきましょう。
- 🎵 好きな音楽を聴く
- 🚶♂️ 軽いウォーキングやストレッチ
- 📓 感じたことを日記に書く
- 😌 深呼吸・瞑想アプリを使う
- ☕ カフェで気分転換
「働き続けるには、セルフケアも仕事の一部」という意識が重要です。
📣経営者の皆さまへ:相談の第一歩を社労士と
メンタル不調や離職の背景には、人間関係・評価制度・労働時間・業務設計など、
企業側で対処できる部分が多くあります。
「うちの社員も五月病かもしれない…」
「でもどう対策すれば?」という経営者の方へ。
社会保険労務士は、法的手続きだけでなく、「人が辞めない職場づくり」のお手伝いができます。
福岡市東区を拠点に、地元の中小企業さまに寄り添ったサポートを行っています。
📞まずはお気軽にご相談ください♪
✔️ 顧問契約のご相談
✔️ メンタルヘルス体制の構築
✔️ ストレスチェック導入・活用法
✔️ 社員向けメンタル研修